5月21日(月)の早朝、金環日食が起こります。国内では25年ぶりの現象ですが、前回観察できたのは沖縄県の一部だけでした。そして今回を見逃すと、次回は18年後の平成42年(2030年)、ただし北海道のみです。なお群馬県内では天保10年(1839年)9月8日以来で、次回は2386年10月24日です。自分が住んでいる場所でこのような日食を観察できるチャンスは、まさしく一生に一度と言えるのです。
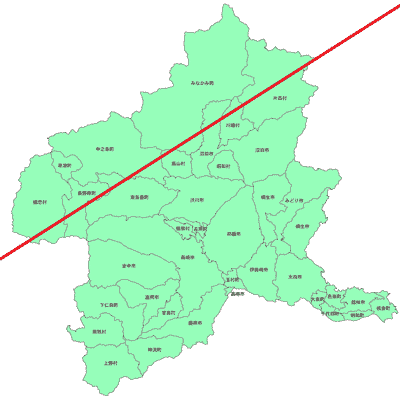
さて、右図の赤い線は、今回起こる日食で“金環”が見られるか見られないかの北限界線(予報)を示しています。この線よりも南側では金環になり、北側では金環にならず、極めて深く欠けた部分食となる予報です。しかし、大きな狂いは無いものの、実際には、月の形や重心、クレーターなどの地形、実際の太陽の大きさなど、使用するデータや不確定な要素のために、予報どおりにいかない場合が十分考えられます。また、実際には“金環”になっていても、観測方法によっては“金環になったかどうか”を確認できない場合も考えられます。
そこで、“金環日食の北限はどこだったのか”という共通テーマを掲げ、群馬県内の子どもたちや教職員の皆さんと、ぐんま天文台の協働により、調査・考察したり、情報交換をしあったりすることを通して、子どもたちの宇宙や自然現象への関心を高めたり、考察力や表現力を高めたりすることにつなげたいと考え、この企画を考えました。群馬県の子どもたちが相互に連携しあい、主体的に観測に参加する機会とすることに最大のねらいがあります。主人公はあくまでも“子どもたち”であり、ぐんま天文台はそのお手伝いをさせていただきます。
具体的には、各観測点(学校)ごとに“金環になったかどうか”をいろいろな観測方法で判定していただき、結果を報告していただくわけですが、限られたわずかな瞬間の出来事に、息をのみ、注視する姿勢は、子どもたちの観察力・集中力を高めることにもつながるでしょう。また、その瞬間を共に過ごし、感動を共有することの素晴らしさも味わえることでしょう。さらに、大人が見逃してしまうような大発見もあるかもしれません。このような調査は全国的に見ても例が無く、たいへん意義深いものと考えます。
各校からの報告をぐんま天文台職員がまとめ、ぐんま天文台webページにて公開します。参加校には、全観測データを提供します。自由研究などでも活用できます。「日本天文学会」および「天文教育研究会(全国大会)」でも発表を予定しています。
是非、多くの学校に参加していただき、皆さんで感動を共有していただきたいと思います。
なお、“金環”になった状態でも太陽の光は非常に強烈ですので、観察に適した方法を必ず準備してください。ロウソクのすすをつけたガラス板や黒いビニール袋、一般的なサングラス等は危険で、失明の恐れもあります。観察方法の詳細については、下記を参考にしてください。
4月末日までにお申し込みの場合、ぐんま天文台オリジナル「ピンホール式日食投影しおり」をプレゼントします。(先着5万名、学校単位での参加を基本とします。)
具体的な観察器具の製作や留意点などについて、事前に研修を行いたいばあいは、天文台までお早めにご連絡ください(電話 0279-70-5300)。群市や市町村単位、または近隣の数校合同での有志教員向け研修会を1〜2時間程度で実施いたします。平日の放課後でも可。費用はかかりません。
群馬県は「金環」が見られる地域と見られない地域の境目にあたります。
群馬県で「金環」が見られるのは午前7時33分から36分までの間で、時刻は観測地点により異なります。
| 金環が見える場合 (太陽がリング状に見える時がある) (右の図の中央) | 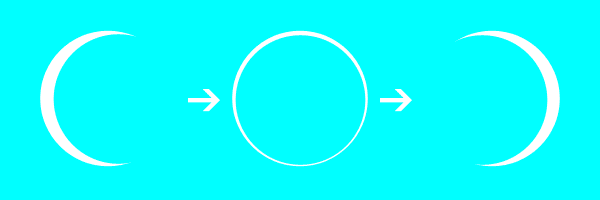 |
| 金環が見えない場合 | 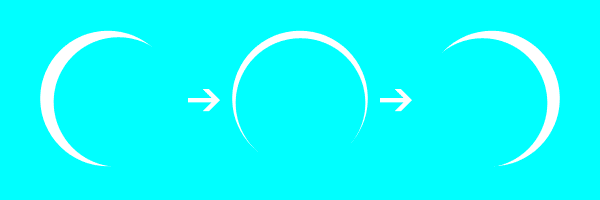 |
皆さんの学校や施設では、「金環」が見られたでしょうか?下のフォームから報告をお願いします。(報告にはパスワードが必要です。)
パスワードを正しく記入しないと報告できません。
ぐんま天文台
所在地 : 〒377-0702 群馬県吾妻郡高山村中山6860-86
電話 : 0279-70-5300
FAX : 0279-70-5544